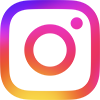 Instagram
Instagram Facebook
Facebook
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ポスト・荷物受け・新聞受けなどに投函・配達します(入らない場合は持ち戻ります)。
インターネットで荷物の追跡情報を確認できます。
日時指定には対応しておりません。
| 地域 | 送料(税抜) |
|---|---|
| 全国一律(日本国内に限る) | 350円 |
税抜金額5,000円以上お買い上げで送料無料。
全国一律送料:税抜700円
上記送料は2kgまでの料金です。
税抜金額5,000円以上お買い上げで送料無料。





